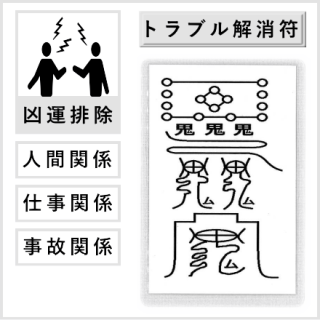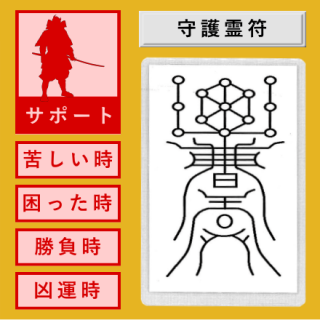お守り、お札、霊符で大事と思われる事、抜粋4点をQ&Aで記します。
Q1・お守り、お札、霊符の持ち方に決まりがあるのですか?
A1・神社、お寺等から購入したお札(神宮大麻【伊勢神宮で奉製されるお神札】等)は神棚に飾るのが最も良いとされます。神棚が自宅にない場合は南向きまたは東向きになるようにし、目線より高いところに置くのが基本です。 家具の上などに置く際には汚れをきれいに取り除いてから、白い布を敷いた上に立てかけます。当山お守り神社が取り扱う霊符類は、ごく一般的なお守りと同様に、お札に比べ大きくはありませんので、基本的には佩帯(はいたい)符法です。佩帯とは身におびる、腰につけることを意味します。ポケット、バッグ、財布などに入れて持つようにすれば良いだけです。男性は身体の左側、女性は身体の右側に霊符が所持できるようにすれば、効果はさらにあるとされています。
ほとんどが佩帯符法で事足りるのですが、室内や門柱に貼ったりする霊符類もあります。これは貼懸(てんけん)符法と言い、お札の場合と同じく目線より高いところに貼るのが基本です。魔除け邪気除け類の符は、家の中で雰囲気が悪いと感じる場所に貼ります。家内安全符類などは、逆に感じの良い場所に貼るのが良いでしょう。
呑服(どんぷく)符法という符を呑む方法もあるのですが、当山お守り神社が取り扱う霊符類の形式には関係ないので省きます。
Q2・願かけ、霊符は他人に見られても大丈夫ですか?
A2・基本的にはダメです。呪文、霊符、書物含め未知のパワーが削がれてしまいます。願かけ、霊符は「人には見せない」が原則です。ただし、霊符の類によっては、魑魅魍魎がうごめく感じの悪い場所に貼るものもあるので、否が応でも見えてしまいます。この場合は自分から符を貼った意味など、吹聴するのは厳禁です。Q3・お守り、霊符の効果効能はどのくらい続くのですか?
A3・お守り、霊符の効果効能は明確な期限が決められているものではありません。神社、お寺などでお正月に購入された御札類は、翌年の初詣の時に返し、新しいものと取り替えるのが一般的です。当山お守り神社が扱っている霊符類はラミネート加工したものなので汚れや破れに強く、極端に傷つかなければ霊験は数年続くでしょう。ただし願望を達成した場合などは期限と考え、次に備えた符を準備するのも必要です。Q4・不要になったお守り類の処分はどうすれば良いですか?
A4・神社、お寺等から購入したお札類の返納先は、お守りを授与した神社やお寺が基本です。 自分で寺社に出向き、直接返納することで感謝の意を表しましょう。 神社、お寺には、お守りを返すためのスペースが設けられています。 当山お守り神社の霊符に関しましては、ラミネート加工をしている関係上、お焚き上げで感謝の浄化をすると黒くドロドロになってしまいますので、控えた方が無難です。ではどのように浄化処分するのかは、色々な考え方があります。当山お守り神社では次の方法を推奨していますので、実行してみてください。
符を最初は上部左側を横から切り、次は縦に上部左側から切りを繰り返し、霊符と分からないバラバラ状態のまま白い紙に包み、白色のビニール袋に入れます。もちろん単体で他のものは入れないで下さい。当然ですが、感謝の心を込めてこの作業を行うのです。
上記の作法は、九字護身法(臨、兵、闘、者、皆、陣、列、在、前 の九つの文字からなる密教での邪気を払う真言のこと)に近いものがあります。しかし九字に断定したものでなく、霊符と分からなくするための作法ですので、感謝の気持ちをもとに切ってもらえば良いのです。ただし五回以上切断した方が、元が何か分からなくなるので当山としては推奨します。

後は各自治体のごみ収集方法に従い出してください。ごみという言葉に嫌な感じを受ける方もいるでしょうが、ごみは元々が何かの役に立ってからその役目を終え処分されるものです。生ごみなどは正しく私達の命の基になった食材最後の姿です。これを不浄なものと表現する方もおられますが、とんでもないことです。役目の終わった霊符を、各自治体の決まりに従い拝送することは、罰当たりな行為ではありません。古の法則に則りお焚き上げをし、灰にしたからといって山中に埋めるとか、川に流す行為の方が現代では不法投棄に近いものがあります。
尚、直接返納という考えから、当山お守り神社発送所に送っていただいても構いません。大切に心を込めて供養いたします。