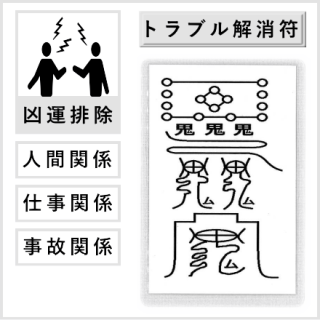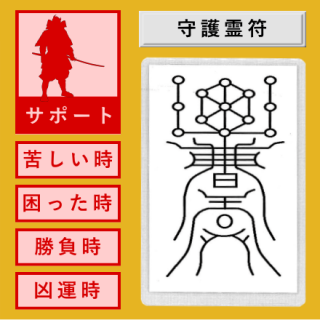厄年について
厄年の歴史
平安時代の書物「源氏物語」「栄華物語」「水鏡」及び江戸時代の「和漢三才図餌繪」などで厄年の記載がされています。掲載されている厄年は7・16・25・34・43・52・61歳となっています。明治以後には現代と同じ男性25歳・42歳・女性19歳・33歳という概念が確立します。中国古来の陰陽道に端を発した厄年ですが、科学的な根拠や由来は不明確で曖昧です。しかし当時はもとより現代に至るまで、長い年月に渡り厄年の風習は私たち人間の生活に大きな影響を与え続けているのです。現在では男性42歳、女性33歳の大厄を一番重要とする厄年の考え方が一般的になっています。
厄年は節目
科学が進歩し、ネットの情報がいろんな人に行きわたることで、迷信、俗説は日常生活の中からどんどん消えているのが現状です。しかし厄年については非常に気に掛ける人が多いのも事実です。社会生活の中での健康や障害が何らかの形として現れる時期で、転機や変化と感じたり、遭遇することも多くなるのは不思議です。こうした人生の「節目」となる年齢を「厄年」とし無理をせず、自重しながら大過なく慎重に過ごすのが、厄年の意味です。
前厄・本厄・後厄
男性大厄、42歳を本厄とするとその前後に前厄、後厄があります。女性大厄33歳を本厄とすると、その前後に前厄、後厄があります。厄年をそれ以外に見てみると、男性と女性では男性25歳・61歳、女性19歳・37歳と近年の習慣では語られることが多いと思われます。当山では方位学(気学)を多少なりとも重視している面があるので、厄年と方位学を重ね合わせた面から、男性42歳大厄と女性33歳大厄は方位学的(離宮前厄・坎宮本厄・坤宮後厄)にも重なっています。しかしそれ以外はなぜその年齢に厄が訪れるのかは、いま話題の2023年ジェンダー論からも導くことは出来ません。(方位学から強引に説をコジツケルことは出来るのですが)そもそも男性42歳が4・2と続くから死(しに)にとりなして忌むと言ったり、女性33歳が3・3(散々)と重なるから大変だ!みたいな語呂合わせが用いられたとする考察があることにより、由来の曖昧さを増加させてます。
当山お守り神社としては、方位学的に考察が一致している男性42歳と女性33歳時の大厄がとても重要と考えております。しかし過去から語られている厄年も、何かしらの意味があるのでは?と否定はしません。厄年の前後は、警戒するに越したことはありません。
厄年とは天運味方せず(会社・仕事・人間関係・病魔・怪我・事故で悩み事が多発する時期)です。
大厄(男性42歳・女性33歳)前年に前兆(オーメン)が表れてくるので、その兆候を見逃すことなく慎重に毎日を過ごすのです。本厄は当然ですが、前後の厄年時もより慎ましやかに、環境を変えることは極力避けるようにしましょう。
例えば、このようなことは避けるべきです。
・引っ越し
・新築
・結婚
・転職
・会社設立
・新しいことのスタート
上記のような出来事は心身ともに大きなストレスが掛かりやすく、体調の転機となる時期に負担を与えやすいという共通点があります。なるべくなら自重するに越したことはありません。
本厄年後の延長線上にある後厄時には、他力本願に重きを置くことが無事安泰の鍵となるでしょう。前厄、本厄の重圧を乗り越えた肉体精神はとても疲弊しています。最後の後厄は「他力本願」に頼っても良いのです。他力本願とは人それぞれですが、此処を読んでいる方との縁やお守りが、「他力本願」の一つだということは言うまでもありません。
厄年を迎えた方は、その事象が現代では複雑かつ深刻化が顕著です。近代化が情報のスピードを生み、他愛無い行動が是非(正しいことと正しくないこと)を生みます。是非の判断が難しい時は(恥ずかしいと思わず)他人の意見を聞くことです。
厄年=役年(役に立つ年)
人の役に立てる年齢を迎え、重要な立場になる時との考もあります。いずれにしても、無理を強いられる時で体調が影響を受けやすいといわれることには変わりありません。
今まで以上に万全の準備ができれば新しいことにチャレンジするのも一つですが、状況の変化が厳しい、つらい、難しいと感じたら時期を外して休息、充電するのも一つの選択肢であり勇気です。
転勤、転職など避けられない環境の変化がある場合は、厄除けや厄払いへ行って厄落としをすると不安も軽減し、前向きに取り組めるようになるでしょう。ストレス軽減(厄除けや厄払い中は無になれることが多い)にもなるので一石二鳥です。
30代の女性は、厄年が6年間もある?
33歳の大厄を前後して3年、37歳の本厄を前後して3年の計6年間(35歳だけは厄的には無風)も厄年が続くという考察があります。なぜ女性だけこんなことに?男性も外で家族のために必死で働いているのですが、女性はここに育児まで抱え込んでしまうからだと思われます。共働きの場合でも、結局は女性の方が家事と育児を負担していることが多く、男性は社会的にもイクメン(育児休暇を取得して子どもとの時間を楽しむ)が浸透しているとはとても思われないからです。さらにこれは男女共ですが、親がシニアになり病気(認知症等)、怪我、介護が必要となってくる時期でもあります。様々な要因が重なり、30代の女性は大変だという考えが、過去、現在が一致しているのは、やはり何かがあるのでしょう。10代は基より、20代の時より少しだけでも注意を払いながら生活しましょう。
満年齢と数え年の考察
満年齢とは生まれた時が0歳という考えで、数え年とは生まれた時を1歳とし(受胎した時から時間の経過を含むという考え)、正月や誕生日が来たら歳が増えていくという思考です。当山としてはやはり生命を受けた時(確立した時)からの時間経過が重要と考えております。
厄年の重要性を謳っている神社仏閣の大多数が、数え年を採用しているのは大変重要なことであり、当山お守り神社も数え年で厄の進行を判断しています。
数え年と満年齢の計算方法
生まれた最初の年に1歳と数えるのが数え年で、毎年1月1日に1歳年を取ります。満年齢は生まれた日は0歳、誕生日を迎えると+1歳になります。
数え年の簡単な計算方法です。これは、次のように覚えておくとわかりやすいでしょう。
誕生日前→ 満年齢+2歳
誕生日後→ 満年齢+1歳
満年齢の計算方法
西暦をもとに計算する場合は、現時点の西暦-生まれた西暦を引きましょう。たとえば2023-1990=33、その年の誕生日を迎えているのであれば満33歳になり、誕生日前なら1を引いて32歳になります。
厄年の過ごし方
基本的には自重して、静かに過ごすことです。積極的な思考は避ける時です。あくまで普通に暮らすことで良いのです。厄年だからといって気にし過ぎる方が、ストレスをため込んでしまいます。もし失敗等があっても、「厄年だからしょうがない」と逆手に取ることで、言い訳や逃げ道にも使える便利な時期なのです。自分の人生を見つめ直す節目の時と捉え、生活しましょう。